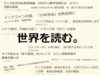- カンボジアをアドラー心理学から考察してみた① 市場で働く女性たちが貧困から抜け出せないのは「恥をかくのが嫌だから」!?
- バンコクの路上で出会った小さな店の経営者4人、“割が最も良い”のは時流に乗った鍵屋だった!
- 【環境と開発の接点(3)】環境意識はどう変える? “目立ちたがり”の国民性を刺激!~「環境のフリーペーパー」を発行してみた~
- 【環境と開発の接点(7)】途上国でも環境はブーム! その実態とは?~イベントの「中身」と「後」を考察してみた~
- 企業はSDGsを通して国際協力のアクターとなり得るか~SDGs書籍の著者に聞く第6回~
- カンボジアをアドラー心理学から考察してみた② 「〇〇をする」という気持ちが貧困脱却を可能にする
 私の数学の授業で、生徒が“先生”になってクラスメイトへ問題の解き方を説明しているところ。間違っても、発表する勇気にクラスみんなで拍手を送る
私の数学の授業で、生徒が“先生”になってクラスメイトへ問題の解き方を説明しているところ。間違っても、発表する勇気にクラスみんなで拍手を送る成績1位なら賞金700円
ンジウ高校は各学期に一度、成績優秀な生徒を豪華ディナーに招待する。ディナーではヤギ肉入りのシチューやチャパティが振る舞われる。普段はギゼリ(豆とトウモロコシを塩で煮込んだもの)やウガリ(トウモロコシの粉を練ったケニアの主食)といった安い食事が中心のンジウ村の人たちにとってはご馳走だ。成績優秀者として常連のクリスティンさん(15歳)は「ソーダまで飲める」と満面の笑みをたたえる。
成績優秀者は加えて、賞金ももらえる。賞金は、成績が1位の生徒から順に600シリング(約720円)、500シリング(約600円)、400シリング(約480円)、300シリング(約360円)、200シリング(約240円)、100シリング(約120円)と6位まで。また成績が少しでも上がると100シリング(約120円)がもらえる。
ンジウ村の物価が食パン1斤60シリング(約72円)、1カ月の家賃2000シリング(約2400円)であることを踏まえると、生徒にとって賞金は「大金」。嬉しいことは間違いないだろう。
ただこのやり方で本当に良いのだろうか、というのが私の疑問だ。体罰や報酬は生徒のモチベーションを高める効果があるかもしれない。だが実態は体罰を受けるのも、報酬を得るのも毎回同じ顔ぶれだ。体罰を恐れても、報酬があっても努力しない生徒は少なくない。より多くの生徒の学習意欲を高めるには別の方法があるような気がする。
生徒が先生役に!
そこで私が参考にしたのが「アドラー心理学」だ。
オーストリアの精神科医アルフレッド・アドラーは「叱ってはいけない。褒めてもいけない」と主張する。褒める行為には「能力のある人が能力のない人を評価する」という上下関係が含まれ、劣等感を生むという。叱ったり褒めたりすることで相手をコントロールすることになる。ズバリ言うなら、ンジウ高校で実践する「体罰=叱る」「報酬=褒める」という動機付けは、アドラー心理学に逆行している。
体罰や報酬の代わりにアドラーが大事にするのは対等な関係であり、喜びや感謝の言葉を伝えることだ。「人は感謝の言葉を聞いたとき、自らが他者に貢献できたことを知る」とアドラーは語る。だれかに貢献したことで「自分には価値がある」と思えたら、自分の課題に自ら立ち向かう「勇気」をもてる。
私が強く意識するのは「他者へ貢献した」という実感を生徒にもってもらうことだ。私の授業では、生徒に先生役を担ってもらうときがある。クラス全員に向けて問題の解説をしたい生徒を挙手で募る。その後ひとりの生徒が教室の前に立ち、クラス全員に問題の解き方を説明する。説明の正誤にかかわらず、発表した勇気に対して先生役をした生徒へクラス全員で拍手を送る。