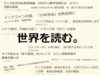ガーナのカカオ農園で男の子がカカオの実を鉈で割るところ(写真提供:ACE)
ガーナのカカオ農園で男の子がカカオの実を鉈で割るところ(写真提供:ACE)ガーナの児童労働の問題に取り組む認定NPO法人ACE(東京都台東区)は1月7日、世界各国のカカオ農園を取材し、チョコレートの魅力を発信するジャーナリストの市川歩美さんをゲストに招き、トークイベントを都内で開催。チョコレートの原料カカオの生産国ガーナで児童労働が起きている現状を訴えた。ACEの副代表の白木朋子さんは「チョコを食べるときはカカオ農園で起きていることを思い出してほしい」と話した。
627人が通学できるように
ACEが活動するのは、ガーナ南西部のアハフォ州アスナフォ・サウス郡。支援対象は、カカオ農園の農作業を手伝うため、学校を休む子どもたちだ。子どもを働かせる家庭の多くは、子どものために制服や文房具を買うお金がない。
こうした問題の解決を目指してACEは2009年に、「しあわせへのチョコレート」プロジェクトを立ち上げた。カカオ農家の収入を増やし、子どもを学校に通わせる金銭的な余裕をつくるための支援をする。
例えば、貧しいカカオ農家に対してカカオの木の病気の管理方法や基礎的な栽培の仕方、生産計画の立て方などを指導する。このトレーニングを始めてから、2022年時点ではカカオの農家の収入が最大で約3倍に増えたという。
子どもが継続して学校に通えるよう学校給食の資金も一部負担する。トマトやタマネギと一緒に炒めたガーナの代表料理「ジョロフライス」、蒸したプランテン(調理用バナナ)、ホウレンソウを炒めたおかずなどを村の女性たちが調理し、子どもたちが持参したタッパーに入れて配膳する。「給食のおかげで、栄養不足が解消される。親も安心して子どもを学校に通わせられる」(市川さん)
ACEのさまざまな取り組みが奏功し、村の小中学校の児童・生徒の出席率は、2022年の57〜66%から2024年は100%に上がった。2009〜2024年の16年で児童労働をやめ、学校に通えるようになった子どもは627人に及ぶ。