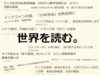ベナン南西部のドボ市中心部にある食堂を営むジネットさん(左から2人目)。多くの人が訪れる
ベナン南西部のドボ市中心部にある食堂を営むジネットさん(左から2人目)。多くの人が訪れるやり方がわからない
ジネットさんから話を聞くにつれ、私は、お金だけの問題ではないのではないか、と気づいた。「食堂でいま出している料理は小さいころ、おばあちゃんから教わったもの。メニューを増やすにも、作り方を知らないからできない」とジネットさんが答えたからだ。表面上の理由としてお金を挙げるものの、その背後には「知識とスキル」が足りない現実も大きなネックとなっているようだ。
お金をもっと稼ぐために新しいことをやりたいが二の足を踏む人はなにもジネットさんに限らない。
ドボ市在住のクウディ・クリスティンさん。2児を育てる28歳の彼女は、家業であるカゴ作りの仕事で生計を立ててきた。収入アップを目指して最近は洗剤や飲み物を売り始めた。副業で手にできる額はわずかだが、小さくて大きな一歩だ。
そんなクリスティンさんでも、次なる一歩は踏み出せずにいる。「本当はカゴ作りをやめて、より稼げる野菜売りになりたい」。ところがそのために何かのアクションを起こしているかといえば、「何もしていない。誰かがやり方を教えに来てくれればいいのに」と受け身の姿勢を崩さない。
現状を変えたい、もっと豊かになりたいと願っていても、行動はしない。いわば諦めモードの村人は少なくない。
ドボ市の取材で例外だったのが、屋台でガソリンを売るイブス・ウィウィさん(20)だ。大学の学費を稼ぐために「儲かると聞いた」ガソリン屋台を始めた彼は、市場の同業者から仕入れ先などの情報を聞き出すことでゼロから店を立ち上げた。開店から3年経ったこの2月には2号店もオープンしたほどだ。
世界一チャレンジしない日本人
ベナンの田舎を舞台に次の一歩を踏み出せずにいる人たちへの取材を進める中で、私はふと気づいた。この問題はベナンだけではない。日本人の若者も挑戦しないといわれることを。
米雑誌のニューズウィークは2015年、「世界一『チャレンジしない』日本の20代」と題する記事を出した。このなかでも、ベナンのケースと同様に、現状維持に甘んじる理由として「知識やスキルの不足」を挙げている。
起業に関心をもつ日本人を対象とした経済産業省の調査でも、「日本の起業家教育は十分に行われているか」の問いに対して、60%以上が「不十分」または「やや不十分」と答え、「環境への不満」を示したという。
こう考えると、ベナン人も日本人も似たようなもの。むしろベナンの田舎と比べ、教育レベルが高く、また膨大な情報にアクセスできるインターネットも整備されている日本のほうがチャレンジする環境的には断然上のはずだ。
にもかかわらず、アクションを起こさず手をこまねいている日本人‥‥。私は「お金を欲しいとは言いながら、実際には何も工夫をしていない」とベナン人を否定的にとらえようとしていたが、その考えはおかしいと改めた。

食堂で売るトマトベースの炊き込みご飯「ジョロフライス」。厚揚げのように見えるのはベナンのチーズ(ワガシ)。揚げた魚の切り身ものっている。左奥のペットボトルは熱湯消毒して再利用しているもので、中身はビサップジュース