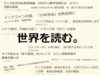ベナン南西部のドボ市中心部にある食堂を営むジネットさん(左から2人目)。多くの人が訪れる
ベナン南西部のドボ市中心部にある食堂を営むジネットさん(左から2人目)。多くの人が訪れるいまに満足して生きる
ここで私は、「ベナンならではの足かせは何か」を想像してみた。パッと思いつくのは気候の違いだ。ベナンは40度近くまで気温が上がる熱帯。しかも扇風機すらない場所も多い。そうした中では体力が奪われるうえに集中力も続かない。やる気を維持するのも至難の業だろう。仕事をせずに木陰で昼寝する人をよく見かけるのもうなずける。
また経済水準が低いのも厳然たる事実だ。カゴ作りのクリスティンさんは食費や家・作業場の家賃を払うのが負担となって貯金ができないという。2人の子どもも学校をやめ、働きに出なければならなかった。
さらにメンタリティの部分でも、日本人とベナン人では工夫や挑戦をしない背景は違うようだ。日本人は先のことを考え、失敗のリスクを恐れるあまり現状維持を望む傾向が強いだろう。
対照的に、ベナンは冬がなく、食べ物も年中生るほど自然環境に恵まれていることもあって「ベナン人は将来の見通しを立てるのが苦手」といわれる。ドボ市に住む日本人女性も「ベナン人は貯金をしない。だから病気になっても、病院での高額な治療は受けられず、安い民間療法に頼るケースが多い」と語る。いまを生きる――これがベナン人だ。
言い換えるなら、いまの生活を犠牲にしてまで将来のために挑戦しよう、というメンタリティを多くのベナン人はもたないのではないか。それなりに現状に満足している、といえるかもしれない。
「奇跡が起きて、望みが叶うことを待っているベナン人は多い」。ベナン人男性が語ったこの言葉に妙に納得がいった。