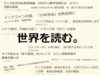燻製の魚がずらり。チップを使わないのに煙がモクモク上がる。ベナン南西部のドボ市フォンコメ村のガウボン・レインさんの家の敷地内で撮影
燻製の魚がずらり。チップを使わないのに煙がモクモク上がる。ベナン南西部のドボ市フォンコメ村のガウボン・レインさんの家の敷地内で撮影ベナンでは燻製の仕方が日本とまったく違う。ベナン南西部のドボ市フォンコメ村で燻製の魚を売る女性によると、日本では不可欠のチップは使わない。直火で、アブラヤシの枝とトウモロコシの葉を燃やして煙を出すだけだ。
トウモロコシの葉っぱが大活躍
この女性の名前はガウボン・レインさんだ。55歳。祖母が魚の燻製を始めたので、ガウボンさんは物心ついたときから母の背中で煙の中に包まれていた。ガウボンさんの家系では女性がこの事業を代々引き継ぐ。「ドボでは燻製は女の仕事。だから息子には継がせない」と彼女は言う。ガウボンさんと一緒に働く5人もすべて女性だ。
魚の燻製にガウボンさんが使うのは自宅の外にある5つの釜。「熱源」と「煙を出す」の2つの役割を兼ねる材料はアブラヤシの枝、トウモロコシの実を包む葉っぱ(包葉。「ほうえい」と読む)、コッポと呼ばれる木くずを使う。アブラヤシの枝は近くの農家から安く譲ってもらう。包葉は農業廃棄物なので無料だ。
アブラヤシの枝と包葉を使うのは、単に手に入れやすいだけではない。煙をたくさん出すからだ。その条件は、「油分が多いこと」(燃えやすいが不完全燃焼に陥ると煙が出やすい)、「繊維質が多いこと」、「水分が多いこと」の3つ。アブラヤシの枝と包葉は燻製の材料には最適だ。
トウモロコシといえばベナンの主食(餅のようなもの。種類はたくさんある)の原料のひとつだ。またアブラヤシは、料理でよく使われるアブラヤシのオイルや国民酒ソダビの原料になる。引っ切りなしに出る廃棄物を活用できる観点から「エコ」とも言える。
ただその半面、チップを使わないので、日本の燻製のようにスモーキーさに加えて、サクラやヒッコリーといったプラスアルファのかおりを楽しめない。

ひとつひとつ魚を並べていくプロセス。魚が脆いため、ていねいに扱う。「あなた(筆者)が持ったら魚は崩れるわね」と手伝わせてもらえなかった

燻製に使うトウモロコシの実を包む葉っぱ(包葉)。無料で手に入るが、なくなったらお金を出して買うという