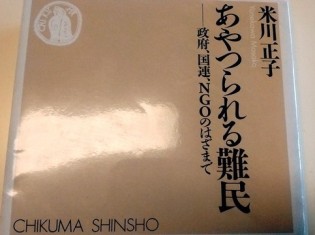
シリアや南スーダンなど中東やアフリカ地域から欧州へ逃れる難民のニュースは連日のように伝えられる。一方で米国のドナルド・トランプ新大統領が就任直後に難民受け入れを一時停止する大統領令を出した。こうした報道の底流にあるのは、難民は国際社会が保護すべき対象だという共通認識がある。だが本書「あやつられる難民―政府、国連、NGOのはざまで」(筑摩書房、2017年2月、940円+税)の著者、米川正子氏は、その国際社会が時に難民を生み出す加害者になっている、と指摘する。
米川氏は、紛争が続いていたルワンダやコンゴ民主共和国(以下、コンゴ民)などアフリカ大湖地域に、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の職員として約10年間勤務した。318ページからなる本書では、現場での実務経験や聞き取り調査、各国研究者やジャーナリストなどの情報から、メディアではほとんど報じられない、難民が直面する実態を詳細に記している。
一体なぜ、国際社会が難民にとって加害者になりえるのか。著者は、難民問題そのものが、人命救助などの単なる「人道問題」ではなく、非常に政治的な側面を持っているからだ、と説く。難民の運命を翻弄する背後には、難民の出身国や受入国の政府、難民を支援する国際機関、国際機関に資金を拠出する各国政府などが存在し、これら国際社会の多様なアクター同士の関係やその利害が大きく影を落とす現実がある。
こうした難民問題の政治性が強く浮き彫りになっている代表例として、本書で詳細に取り上げられているのが、ルワンダ難民だ。
ルワンダは、映画『ホテル・ルワンダ』でも描かれた、多数派民族フツと少数派民族ツチの間で起きた1994年の虐殺事件、その後の民族和解を経て、急速な経済発展を達成した「アフリカの開発成功例」というポジティブな印象が一般的だ。しかし、虐殺事件から20年以上経ったいまも、母国の政情に不安や恐れを抱き、帰還を拒んだり、新たに逃げ出したりする難民が、数十万人以上に上っているという。これら難民には、 フツに加え、ポール・カガメ現大統領が率いるツチ主導の与党ルワンダ愛国戦線(RPF)の元メンバーで、反体制派となって国外へ亡命したツチもいる。
米川氏の聞き取り調査によると、ルワンダ難民が母国への帰還を恐れる最大の理由は、RPFによる市民への人権侵害だ。そもそも94年にフツの難民が生まれた一因は、虐殺事件前の90年から直後の94年8月にかけて、RPFが フツであるという理由で多くの市民を殺害したことにあった、という。一般的に言われる「多数派フツが少数派ツチを虐殺した」という一面だけでなく、RPFを主導するツチもフツに対して、同様に罪を犯した事実を明らかにする。その上で、RPF主体の現ルワンダ政府が「虐殺の予防」という名目上の理由により、2008年に「虐殺イデオロギー法」を策定し、フツのみならず、RPFも虐殺に加担したと非難することや、ツチだけでなくフツも虐殺の被害者だったと示唆することなどを犯罪として定めた、とのことだ。その結果、RPFの犯した人権侵害や虐殺についても、ルワンダ国内では言論の自由が許されなくなり、RPFの戦争犯罪人を保護できるようになった、との見方を示す。
さらにRPF軍は、フツの難民や国内避難民(国境は越えず、国内で逃亡する人々)の中に94年の虐殺を主導した「虐殺首謀者」が紛れていることを口実に、95年にはルワンダ南西部の避難民キャンプを、96年にはコンゴ民東部の難民キャンプを襲撃。多数の無実なフツを殺した。またフツだけでなく、 上記の元RPFメンバーのツチもカガメ政権に命を狙われ、アフリカ各国や欧米に逃亡し続けている。著者によると、RPFが関与した虐殺や人権侵害の真相を知っていて、その情報を外部に公開したか、あるいは公開を予定していたがゆえに、RPFに暗殺された元RPFメンバーもいる。ツチ・フツともにルワンダ難民はRPFに恐怖を抱いており、「現政権が続く限り帰還を望むことはないだろう」と著者は結論づける。
しかし、難民がRPFを恐れるのと同時に、RPFも難民を恐れているという。これには、もともとRPF自体が、59年のルワンダ社会革命後、ルワンダからウガンダへ逃れたツチ難民によって87年に結成されたという歴史が関係している、と本書は分析する。当時難民だったカガメ氏も、RPFのメンバーだった。RPFはフツ政権を打倒するため90年に武力行使でルワンダへ侵攻、当時のハビャリマナ政権(フツ)との内戦へと発展し、それが虐殺につながったという。このように現与党のRPF、そしてカガメ大統領自身が元難民であり、隣国から母国の政権打倒に従事した経歴をもつ。このためカガメ現政権は、過去の自分たちが94年にハビャリマナ政権を打倒したように、現在のルワンダ難民も結束してRPFを脅かすのではないかと恐れている、と筆者は見る。だからこそ、カガメ大統領は難民をルワンダへ帰還させ、国内で徹底的に管理するか、暗殺するかのどちらかを望んでいるという。
難民問題が政治的な側面を帯びるのは、これまで示した難民と出身国政府間の関係のみではない。難民を保護する義務のある受入国政府とUNHCRの関係、受け入れ国政府と難民、難民とUNHCRの関係も政治的な要因になりうる。例えば、96年〜97年には、UNHCRがコンゴ民政府とタンザニア政府とともに、ルワンダ難民の意思に反して「強制帰還」を実施した。それは、難民受入国からの圧力や、難民支援の「資金不足」のため、帰還の押し付けが必要になったためだという。ルワンダへの帰還後にRPFに殺されることを恐れた難民の中には、ルワンダと反対方向へ1000キロ以上徒歩で逃亡した者や、ルワンダに帰還後に再び周辺国へ逃れた者もいた。その逃亡の過程で亡くなった難民も大勢いるという。
こうした過去の帰還失敗にも関わらず、UNHCRは09年、ルワンダ難民に対して「難民の地位終了条項」を適用すると発表した。再びルワンダへの「強制帰還」を試みた。この条項の適用は、ルワンダ難民が難民としての地位を喪失し、これ以上国際的な保護が受けられなくなることを意味する。いまもなおRPF主導の政府への恐怖心を抱く難民にとって、難民地位の喪失は「この世で自分の存在が否定されたこと」を意味し、精神的なダメージが非常に大きいと著者は指摘する。
ルワンダ難民の事例は、他の地域の難民事例と比べ、特殊な部分もある。しかし、複雑な国際政治に翻弄される難民の現状を詳しく学ぶことができる貴重な事例だろう。
本来保護を受けるべき難民は、ときに出身国政府、受入国政府、国際機関、拠出国などの都合や利益に操られ、自分の意思で安心して帰還する時期さえ決めることもできない。国際社会を単純に「中立で善良なもの」と認識するのではなく、難民が直面している厳しい状況を客観的に理解する必要があるだろう。いまなおあちこちで起きている難民問題の実態を描いた本書は、学生や社会人が難民を単に「ニュースの中の存在」ではなく、自分たちと同じように家族を持ち、生きたいと願う生身の人間として捉え直す機会を与えてくれる。
【著者略歴/ 米川正子(よねかわ・まさこ)】
コンゴの性暴力と紛争を考える会代表、元立教大学特任准教授。南アフリカ・ケープタウン大学大学院で修士号(国際関係)を取得。国連ボランティアで活動後、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)職員として、ルワンダ、ケニア、コンゴ民主共和国などで難民保護、支援、政策立案にあたる。JICAや宇都宮大学などを経て現職。著書に「世界最悪の紛争「コンゴ」~平和以外に何でもある国」(創成社、2010年)など。



















